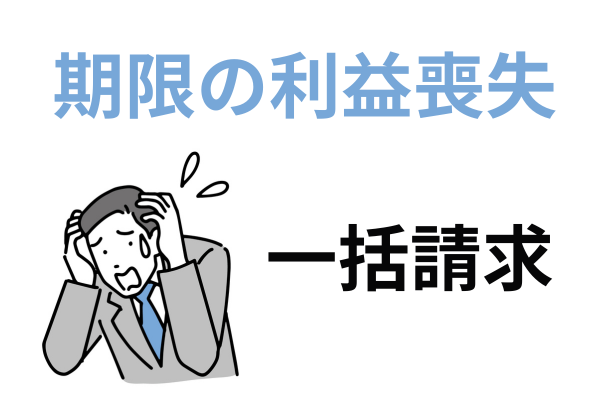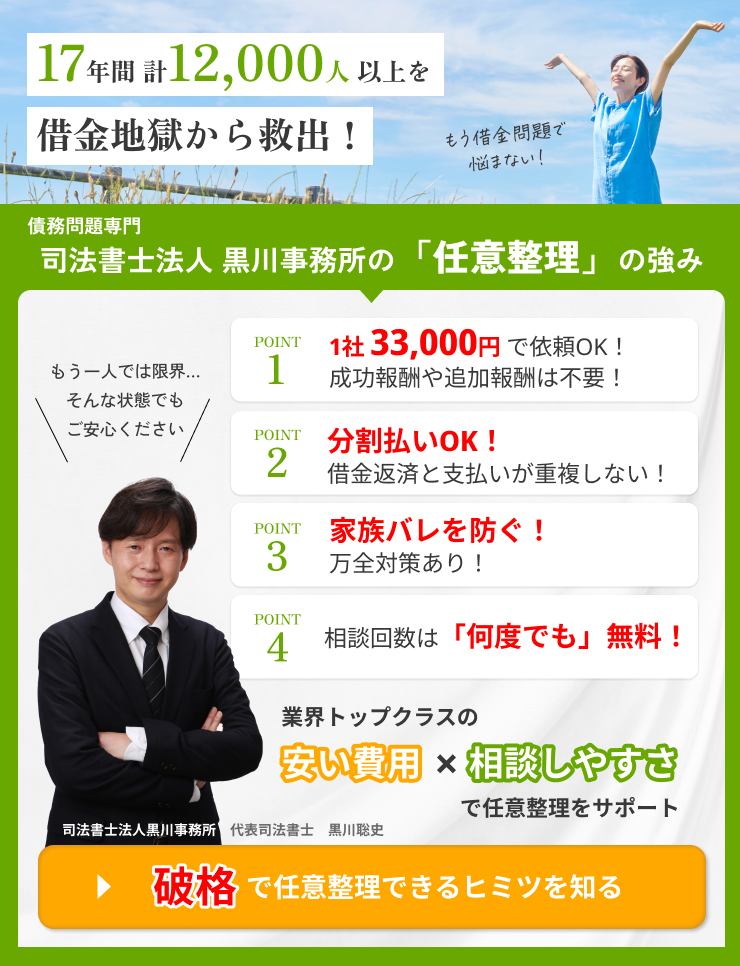平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)

催告書が届いたらどうするべきか?とるべき方法を4つ紹介
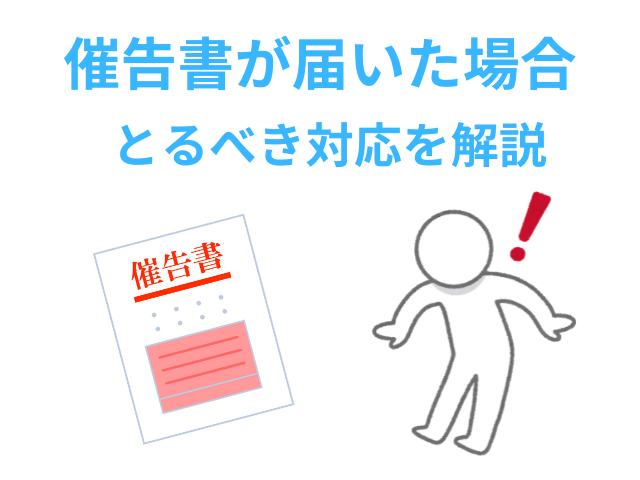
ある日突然、「催告書」という書面が届き、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
「これは何?」「どうすればいいの?」「無視したらどうなる?」など、様々な疑問が浮かぶことでしょう。
催告書は、無視してはいけない通知です。放置すると、状況がさらに悪化し、最終的には財産を差し押さえられるといった深刻な事態にもなりかねません。
この記事では、催告書とは何か、届いた場合に取るべき正しい対処法、そして無視した場合のリスクについて、分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 催告書の内容を確認し、時効が成立するなら時効援用の手続きをする
- 時効でなく返済可能なら、連絡して支払いをする
- 返済困難なら放置せず自分で交渉か、専門家に債務整理の相談をする
催告書(さいこくしょ)とは何か
催告書の目的
催告書と督促状の違い
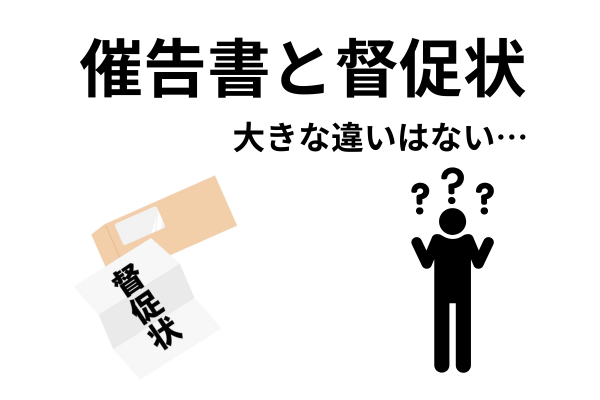
「催告書」と「督促状」は、どちらも支払いを促す点では共通していますが、一般的には以下のようなニュアンスの違いがあります。
- 督促状: 比較的、支払い遅延の初期段階で送られてくることが多い、やや穏やかな支払い要求の通知。
- 催告書: 督促状を送っても支払いがない場合や、より強く支払いを求める最終段階で送られてくることが多い、法的措置を強く示唆する通知。
ただし、これは一般的な傾向であり、法的に「督促状」と「催告書」の効果に明確な区別があるわけではありません。
書面のタイトルが「督促状」であっても、「支払いがなければ法的措置を講じます」といった記載があれば、それは催告書と同様に最終通告と受け取るべきです。
重要なのは書面の名称ではなく、その内容(特に法的措置の予告があるかどうか)です。
催告書が届いた場合の対処法
1. 催告書の内容で心当たりを確認する
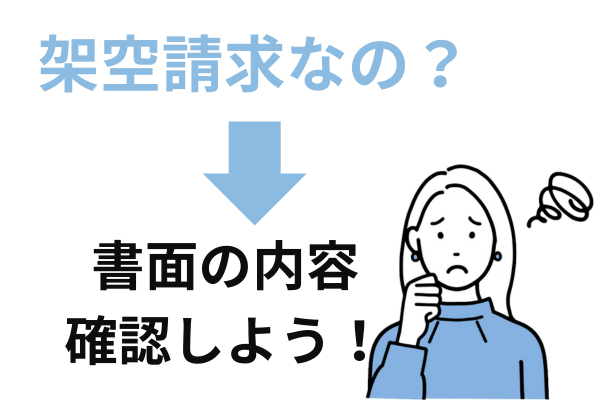
まず、送られてきた催告書の内容をよく読み、何に対する請求なのか、身に覚えがあるかどうかを確認しましょう。
- 請求元の会社名・連絡先
- 請求されている金額(元金、利息、遅延損害金など)
- 契約日や最終返済日などの日付
- 支払い期日
最近では、実在する会社名を騙った架空請求も増えています。全く心当たりのない請求であれば、安易に連絡せず、消費生活センターに相談しましょう。
●ただし、注意点もあります。
「知らない会社名だな」と思っても、債権者が社名を変更していたり、債権を別の債権回収会社(サービサー)などに譲渡しているケースも少なくありません。
この場合、譲渡を受けた会社から請求が来ることになります。社名に心当たりがないからといって書類を破棄せず、送られてきた書類やネット検索で情報を確認しましょう。
2. 書面の内容から消滅時効が成立するか確認する
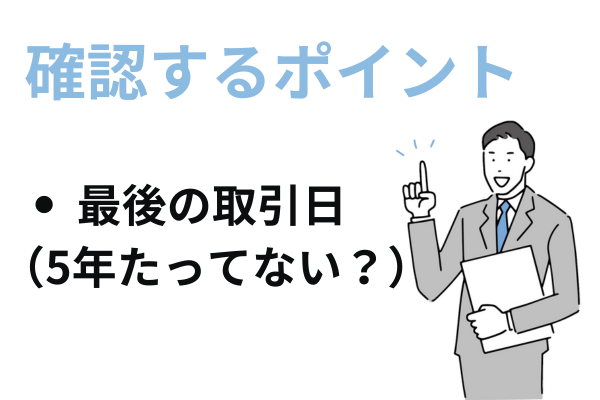
次に、請求されている債権が「消滅時効」が成立しないかを確認しましょう。
借金などの支払いには時効があり、一定期間(多くの場合は最終取引日から5年)が経過しており、「時効なので支払いません」と主張(時効の援用)することで、支払い義務がなくなります。
催告書に記載されている最終取引日や期限の利益喪失日などから、時効期間が経過している可能性があるかを確認しましょう。
【重要】
自分で判断して安易に債権者に連絡を取ってしまうと、不用意な発言(「少し待ってほしい」「分割なら払える」など)が「債務の承認」とみなされ、時効期間がリセットされてしまう(再度、5年待たないと時効の援用ができない)ケースもあります。
長年払っておらず、時効の可能性があると感じたら、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼することも検討しましょう。
3. 期日までに返済する(時効じゃない場合)
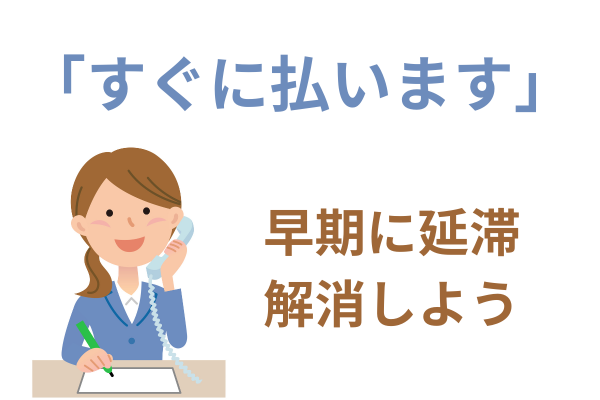
4. 返済が難しい場合の対策
時効が成立しておらず支払い義務はあるものの、請求額が高額で一括での返済が難しい、あるいは他にも借金があって返済自体が困難、という場合もあると思います。
このような場合は、放置せずに対応する必要があります。
選択肢としては、以下のようなものが考えられます。
- 自分で債権者との交渉 分割払いについて自分で交渉することも可能です。会社によっては、事情を考慮して支払い方法の相談に応じてくれるケースもあります。自分で交渉する場合も、今後の利息・遅延損害金の免除や3年~5年の分割払いを目指しましょう。
- 専門家への依頼 弁護士や司法書士に依頼すれば、代理人として債権者と交渉します。任意整理で自分で交渉するより有利な条件での和解(任意整理)を目指したり、状況によっては個人再生や自己破産といった法的な債務整理手続きを検討・提案してくれたりします。
自分で交渉や解決が難しいと感じたら、無理せず早期に弁護士や司法書士に相談しましょう。
1. 信用情報に事故情報が登録される
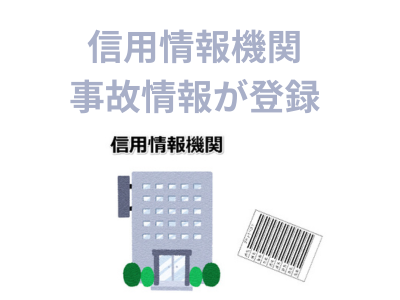
2. リボ払いなど残債務が一括請求される
3. 裁判所から訴状・支払督促が届く

4. 強制執行(差し押さえ)のリスク
判決や仮執行宣言付き支払督促などが確定すると、債権者は裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。
強制執行とは、強制的に債権を回収する手続きです。
具体的には、以下のような財産が差し押さえの対象となります。
- 給与 手取り額の一部(原則4分の1まで)が、完済まで毎月差し押さえられます。勤務先に裁判所から通知が行くため、借金の事実を知られてしまいます。
- 預貯金 銀行口座が差し押さえられ、残高が強制的に引き出されます。
- 不動産 差し押さえられ、競売にかけられて売却代金が返済に充てられます。
- 動産 自宅に裁判所の執行官と債権者の担当者が訪れて、執行官が自宅内を調べて差押でききそうな財産を探して持ち帰り、売却して返済に充てられます。
このように、催告書を無視することは、最終的に生活基盤に影響する強制執行につながる非常に危険な行為になります。
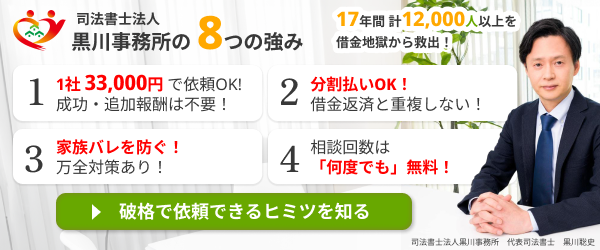
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
催告書が届いたときに弁護士や司法書士に相談するメリット

この記事の執筆者

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
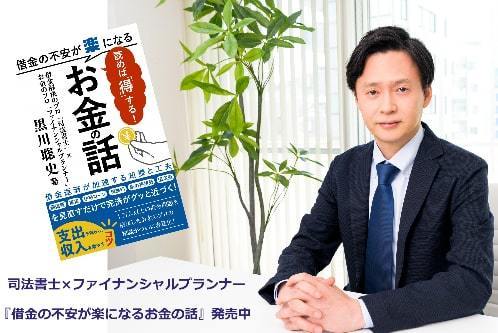
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
- 業界トップクラスの安い費用
- 着手金不要で分割払いOK
- 借金問題専門で18年以上の実績
- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)
平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
司法書士法人黒川事務所
平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
(新宿オフィス 新宿駅7分)
東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階